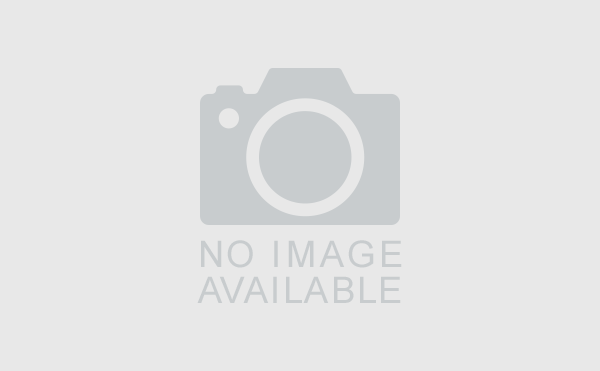令和フィルムカメラ(11) 直らなかったヤシカハーフ17

ヤシカハーフ17、というカメラのお話。
国産ハーフサイズカメラのメジャーどころが段々と集まって来たのもあり、
ヤシカ44という2眼レフカメラでヤシノンレンズの描写が気になったのもあって
ヤシカのハーフサイズカメラが欲しいなと思っていたら発見したこちら。
ジャンクで800円。

ボディーの金属部分にサビあり、くすみあり。
レンズ汚れ、シャッター開かず、ファインダー内のメーター動かずのジャンク品。
後学のため、と購入してあれこれしてみたのですがまあ大変でした。
自分で次に分解する時のメモとして(やるのか?)参考になればとメモ書き程度に
書いておこうと思います

軍艦部からいきましょう。左右側面と裏側のネジが3本。長さが一本だけ違うので注意。
上面のISOダイヤルのカニ目を外して金属板とワッシャー等を外すと軍艦部は外れます。
ダイヤルをどっちかに回しきっておけば出っ張りを合わせて締めるだけなのでそんなに難しく無いはず。
フィルム枚数のカウントがリセットされない不具合が多いようです。


カウンタ中心のネジと手前のネジを外します。
かかっているバネを外してカウンタのギアを取ると下側にあるパーツ。
ここが固着しているので裏蓋を開けた時にリセットがかからないケースが殆どのようです。
汚れを綺麗に除去してあげれば大丈夫。
次にレンズ部分の分解です。

カニ目でリングを外して下を向けるとポロリとリングが落ちてきます

3本のネジを順番に外していけばシャッター部分に辿り着きます
ここまでは簡単。

ここまで外して最初にやるのは写真4時部分の青い丸で囲んだところ
ここにワッシャーがあるのでこれを探して確保することです。
(この写真では早速紛失しています)
外したリング側についてるかもしれませんのでしっかり確認。
これが無いとしたら以前に分解されているかもしれません。

こんなワッシャーが入っています
シャッタースピードですが先ほどのワッシャー下にある金属の丸い部分。
ここがフライホイールになっていてシャッター兼絞り羽根を開閉する事で
プログラムシャッターを調節しています。

ここの油切れかシャッター羽根の汚れ張り付きが原因のようで
注油して何度か空シャッターを切ったところ開閉するようにはなりました。
レンズはこの状態で回せば外れます。ヘリコイド式なので無限遠調整は不要。
後玉はレンズボードごと外して裏側からカニ目でアクセス。


セレンは電圧を測定したところ殆ど数値が出ておらず。
プログラムシャッターが機能しないのは電池が原因とわかりました。


100均のソーラー電卓から太陽電池を外してきてセレンと交換しようとしましたが
これがなかなか難しい

配線を足して現物合わせではんだ付けすればいいか、と安易に考えていたのですが
配線の取り回しが思った以上にシビア。
カメラの上部に乗っている金色部分が露出計ユニット。

露出計ユニットの裏側から配線が出て、露出計底面にある隙間を通って
前面のレンズ部分に配線がいきます。
レンズユニットの細い穴を通して前面に配線を出してセレン電池にはんだ付けするのですが
一度配線を切ってしまうと軍艦部を外してファインダーを外し、
露出計を外して配線をつけて取り回しをしないといけない。

更に言うと青い配線がストロボ用なのですが、これはシャッターユニットを更にばらして
別の穴から通さないといけない。とても大変。
ストロボは使わない、と決めて諦めてしまえばいいのですが安易に配線を切るのも考え物。

結局この配線の取り回しがうまくいかずだったのです。
何とか配線を通してみたのですがヘリコイドに引っ掛かってしまい被覆が剥けてしまいました

組み付け時にヘリコイドを無限遠にあわせて隙間に沿って配線を通すか

逆に最短位置にあわせて配線がかかる部分をリングの下に逃がして
配線しないといけないようです。
前後しましたが配線を通すにはレンズボードを外す必要があります。

前面の革を剥がしてセルフタイマーのパーツを外してネジを4つ外します。
この際に露出計周りのパーツとレンズの位置関係をちゃんと覚えておかないといけません
レンズボードについてくる鍵型の押さえパーツの向き。
ファインダー内にヘリコイド位置を写す指標を動かすアームの位置(手前になります)
ファインダーの上に貼ってある覆いの紙を剥がしてあります。
ファインダー部は露出計の針が手前、ゾーンフォーカス指標と露出アンダーの赤ベロは中側。

レンズボードのアームの裏に細いバネがあります。向きはこの状態。真っすぐな方がシャッターボタン側。
組付け時にシャッターボタン部分に入り込んで曲げそうになるので注意。


レンズボードを外すには底面を外さないといけません。ネジふたつ外してカバーを取り
巻き上げ部を連結するC型の押さえ金属。ここを外します
これで完全に分離します。

何度か外しているうちにこれをカメラ内に落としてしまい、最終的に見つからず。
直らなくなってしまいました。しょんぼり。
自分のミスとはいえあのパーツはどこへいってしまったのか。。

ファインダーと露出計です。上部の覆いの紙を剥がしてファインダー内のネジをふたつ外して
露出計ユニットを固定してあるネジをふたつ外せば本体から外せます
ファインダーと露出計、一緒に外せば針を曲げる心配はないです
ただ細工をしたり中を修正しようとすると結局外さないといけなくなります。ここも面倒。

正面から。

緑の丸で囲んだ部分が露出計の針。
セレンの電力を受けてこの針が動きシャッターを押すと上下の板で針を挟み込みます
(通常は開放されている)
その時のアームの位置でシャッタースピードが決まり、併せてファインダー内の針も動く
大体そんな構造。

この露出計ユニットを筐体にネジ留めするのが厄介でして
ネジに遊びがあります。ちょっと左右に動きます。
この写真で言うと左側(カウンタ側)に寄せすぎると、露出計の針を挟んだままになり
プログラムシャッターが機能しません。
右に寄せすぎるとファインダー内のゾーンフォーカス指標が左側にずれてしまい
表示されなくなってしまいます。微妙な位置調整が必要。

ファインダー内の針が連動して動かないのは写真の丸部分、ここのバネが外れていました。
結局のこのバネをかけようとして針を曲げて折ってしまったので繊細な作業が必要です。
全体的な流れとしてはセレンに配線をしてレンズユニット内を通してレンズ全体を組み上げて
カメラ本体にネジ止めした後で配線を通してヘリコイドが配線を噛んでいないか確認して
Bモードでシャッターが開くか確認して(レンズボードの取り付け位置がずれるとアーム位置がずれます)
露出計を乗せてはんだ付け、という組み方をすれば間違いないんだろうな、と推測出来ます。
出来ますが。。難しいなあ。
組み付ける前は露出計の針が動いていたのに、レンズボードをネジ留めすると
露出計が動かなくなってしまう事が何度もありました。
回路的にボディーにアースを取るのではなくプラス接地らしく、
露出計の配線が芯線が剥き出しの網線なのでどこかショートしていたのかもしれません。
その箇所を発見することは出来ませんでした。
仕組みは分かってもうまくいかず。
結局セレンがダメになっていたのでプログラムシャッターは機能せず、
マニュアル撮影は出来ないので動かなかった、という事になるのですが
もう少しスキルがあったら変わったのかもなあ、と思ったり。悔しいです。
状態の良い個体を見かけたら再チャレンジしてみたいなと思っております
悲しいことなのですがカメラは直らないこともありますね。。
次に直すカメラのスペアとして取っておくことにします。